
世界各国から150名が集い、スラビチェック先生、佐藤貞雄先生のコンセプトを軸に、基礎から臨床応用まで幅広い講義が展開される5日間。

毎年1回、臨床の現場を離れて、自分の「知らなさ」と向き合う貴重な時間です。

特に楽しみなのが、参加者同士の食事をしながらのディスカッション。
普段とは異なる環境の中で、互いの知っていること・知らないことを語り合い、さまざまな疑問をぶつけ合います。
そんな中、ある懇親会の席で、私は佐藤貞雄先生にふと質問を投げかけました。
そのとき返ってきた言葉が、今もずっと心に残っています。
「君が思いついたことで、新しいことなんて全くないよ」
ハッとするような一言でした。
佐藤先生のように、ある一つのテーマについて
過去をすべて調べ上げ、
何が分かっていて、
何が分かっていないのか、
そしてこれから何を調べるべきかを把握している人。
そんな人の前で、浅はかに分かったような物言いをしてしまったときに、浴びせられる痛恨のひと言でした。
「確かに」と、
ただ静かに頷くしかありませんでした。

「無知の知」―自分が何も知らないということを自覚すること。
言わずと知れたこの言葉も、日々の臨床や日常の忙しさに流されていると、ついつい忘れてしまいがちです。
複雑な世界をすべて理解するのは不可能だと、頭では分かっている。
「無知の知」を意識しているつもりでも、深く理解している人からすれば、若輩者の発言は思考の深みに欠け、浅はかな質問に聞こえてしまう
――それが現実です。
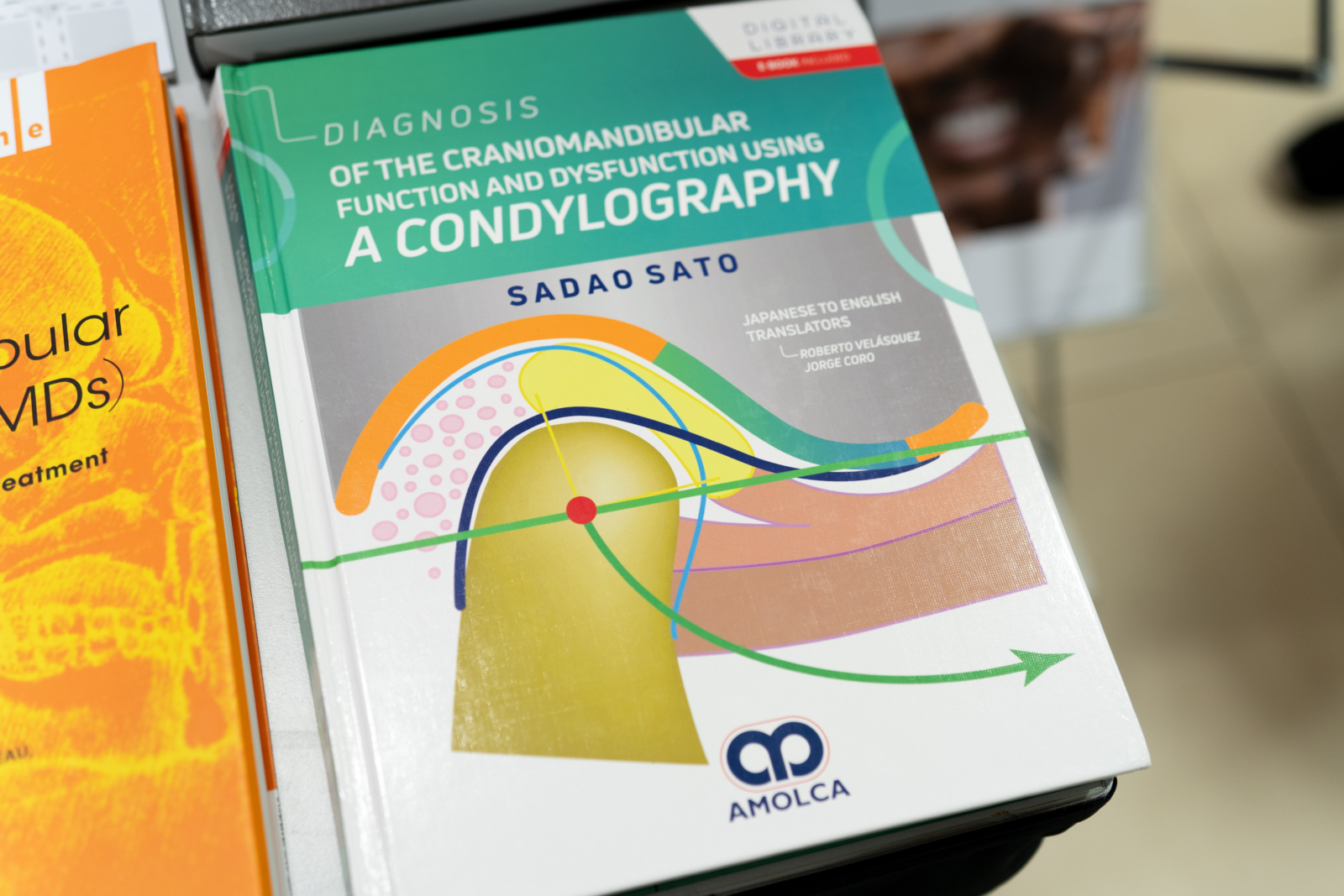
初めてサマースクールに参加したのは2014年。
参加するたびに、この「無知の知」を再認識させられます。
臨床の現場を離れ、学びに没頭できるこの時間は、新しい視点を得る貴重な機会でもあります。
普段と変わらない日常でも、新しい視点が加わるだけで、自分の見えている風景に、わずかな彩りが加わる気がしています。
多くの悩みは、実は“視点の欠如”から生まれているのではないか。
少し違う角度で物事を見れば、あっという間に解決してしまうこともあります。

ものごとを見る視点が増えれば増えるほど、人生は豊かになる――そう確信しています。
そして新しい視点は、意図的に日常を離れ、今の自分を外から眺めない限り、得られないものだとも思っています。
だからこそ、日々の臨床の中にも、“新しい視点”を取り入れ続けることが大切だと感じています。

臨床経験を重ねることで、目の前の患者さんへの対応は、なんとなくできるようになります。
患者さんの望みに対して、自分が提供できることの範囲が見え、その範囲の中で日常が過ぎていく。
現代日本の医療サービスという枠組みの中では、自分なりに少しは機能を果たしている――それは確かだと思います。
けれども、目の前の疾患の原因、予防法、治療法について、本当に何か分かっているのか?
と問われれば、ほとんど分かっていないのが現実です。

元気でいられる限り、あと20年以上は臨床を続けたいと思っています。
「無知の知」を再認識し、
知的好奇心を持ち続けることができれば、
常に新しい視点が得られ、
20年後もきっと、楽しく仕事をしているのだろうと感じています。
